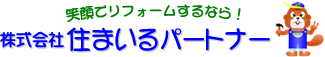左右の壁間の間口に合わせて幅ピッタリに広げたキッチンリフォーム
⑥ キッチン・LDKの
カビ取り・除菌・防カビ処理
キッチン・LDKリフォームのカビ取り・除菌・防カビリフォームは住まいるパートナーへ
当ウェブページを初めてご覧になる方へ。
このウェブページでは、弊社が施工した『幅1,950㎜のキッチンを壁々間ピッタリの2,535㎜のキッチンに入れ替えたLDKリフォーム』について
『作業の様子』をご紹介しております。
『リフォームの概要』からご覧なりたい方は→『リフォーム概要編』をクリックしてください。
ご希望の方にはリフォーム工事もお受けしています。
さて、早速ご紹介に移りましょう。
どけてショック!食器棚背面壁のカビ取り・除菌処理
何年もの間、動かしたことのない家具の裏側がカビの温床になっているケースがあります。
こちらでも、
食器棚の背面の壁がカビているのを発見しました。

ソフト巾木を剥がすついでに壁紙をめくると

ご覧の通り、壁紙表面だけでなく内部にもカビが回っています。

カビ取り・除菌作業は

カビが生えている範囲よりも一回り広めに実施します。
 薬剤を壁紙の裏紙内部にもしっかり浸透させます。
薬剤を壁紙の裏紙内部にもしっかり浸透させます。
時間が経つにつれカビは完全に姿を消していきました。
 カビ取り除菌作業後
カビ取り除菌作業後
 作業前
作業前
隠れたカビを察知!クロス内部のカビ取り・除菌
壁紙内部にカビが発生した兆候として
- 壁紙表面に薄っすらとクロズミが透けて見える。
- 壁紙の浮き
などが見られます。
窓台に近い丸印の箇所は壁紙が若干浮いています。
 カビが壁紙内部で糊を養分として繁殖すると
接着力が無くなって壁紙が浮いてきます。
カビが壁紙内部で糊を養分として繁殖すると
接着力が無くなって壁紙が浮いてきます。
壁紙を剥がしてみると
 この通り、やっぱりカビが出ています。
この通り、やっぱりカビが出ています。
出窓の天井の際(きわ)も浮いています。

壁紙を剥がしてみるとサッシ枠に沿ってカビが発生しています。

出窓周りは壁紙を貼る前に、しっかりカビ取り・除菌します。


出窓内部の天井は、窓清掃と同時にカビ取り・除菌を実施し、
 それから防カビ処理後に壁紙を貼ります。
それから防カビ処理後に壁紙を貼ります。
天井と壁(梁)の入隅は汚れ?…正真正銘のカビです。
天井がコンクリートの躯体の場合、外壁に近い部分には結露が生じやすく、
 こちらでも壁と天井の取り合いにはカビが発生しています。
こちらでも壁と天井の取り合いにはカビが発生しています。
壁紙を剥がした後、取り合い部分は入念にカビ取り・除菌処理をします。
 天井・高所へのカビ取り・除菌処理は目にしみます。
天井・高所へのカビ取り・除菌処理は目にしみます。
カビの再発を許さない!
鉄壁の防カビ処理工程
カビ取り・除菌処理に続いては防カビ処理となりますが、 防カビ処理はカビ取り・除菌剤の完全乾燥後に行います。
食器棚の背面壁は、梁下から床まで防カビ剤を塗布します。
タップリと薬剤を含ませ、ゆっくりと含浸させます。
 カビ取り・除菌処理同様、カビが生えていた範囲よりも一回り広めに塗り込みます。
カビ取り・除菌処理同様、カビが生えていた範囲よりも一回り広めに塗り込みます。
間仕切開閉壁の枠撤去跡の左方20cmの所から
右側のパネルまでの濡れている部分に防カビ剤を塗布しました。

窓周りの防カビ処理
窓の周囲も防カビ処理します。
 こちらにも薬剤をタップリ染み込ませて塗り込んでいきます。
こちらにも薬剤をタップリ染み込ませて塗り込んでいきます。
薬剤の定着を高めるため、重ね塗りして2度の防カビ処理を実施します。
この際重要なのは2度目の防カビ処理前に、必ず完全乾燥させることです。
防カビ剤をタップリ染み込ませた広い壁面を完全乾燥させるには時間が掛かります。
そこで、送風機やジェットヒーターを使用します。
 ジェットヒーターは灯油を燃焼させプロペラファンで高温の熱風を吹き付けます。
ジェットヒーターは灯油を燃焼させプロペラファンで高温の熱風を吹き付けます。
カビ再発不能!
2度の防カビ処理!
完全乾燥後、2度目の重ね塗りの防カビ処理を実施します。


カビに取り付く隙を与えない!
オリジナル防カビパテ処理
2度の防カビ処理後、完全乾燥を待つ間に、
壁紙を貼る面の下地を整えるパテ打ちの準備をします。
 こちらもオリジナルの防カビパテを使用します。
こちらもオリジナルの防カビパテを使用します。
防カビ処理後の壁が乾いて白くなったら、パテ処理を始めます。


壁紙を綺麗に仕上げるにはパテ処理は1度では済まないこともあり、数度繰り返す場合もあります。


とくに、カビがボード表面から奥深くまで入り込んだ窓周りの壁は、
表面を研磨しているので、防カビパテを練り込むことで防カビ処理層が厚くなります。
 結果、防カビ効果も一層高まります。
結果、防カビ効果も一層高まります。
完全乾燥後、2度目のパテ処理を行います。


壁の段差は分からないほどになりました。
 パテ処理前
パテ処理前
 パテ処理完了後
パテ処理完了後
壁紙施工前のパテ処理が完了したところです。


これで防カビ下地処理は万全です。
さて次はいよいよ、壁紙を貼っていきます。もちろん防カビ仕様です。乞うご期待下さい。
バリアフリーリフォーム 防カビ・防露・断熱 木工事・造作工事 電気 内装 入居時リフォーム その他リフォーム全般
ご相談・お見積を承っております 弊社へのお問合せはこちら
埼玉県朝霞市本町2-7-21-4F